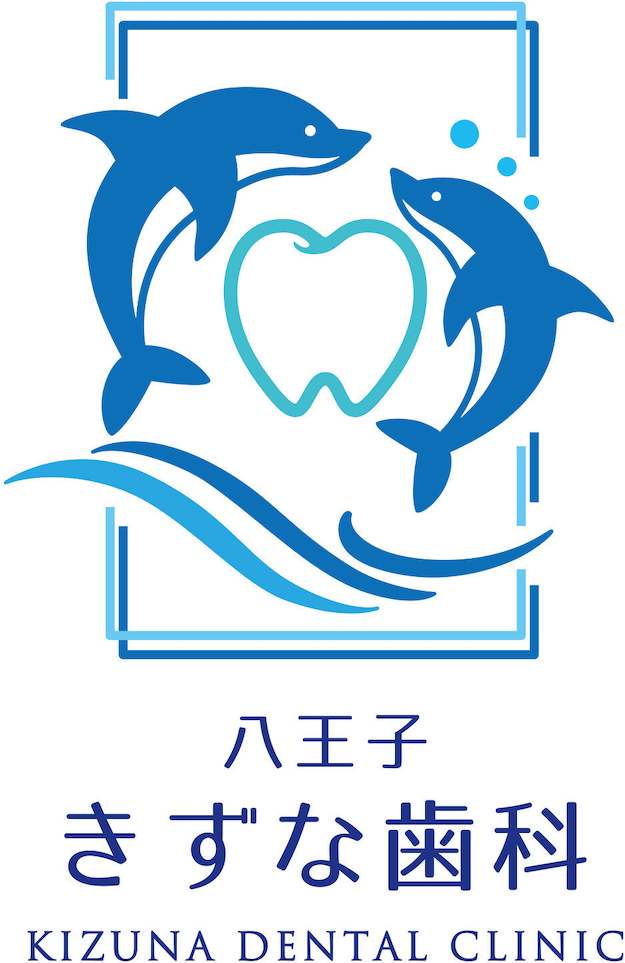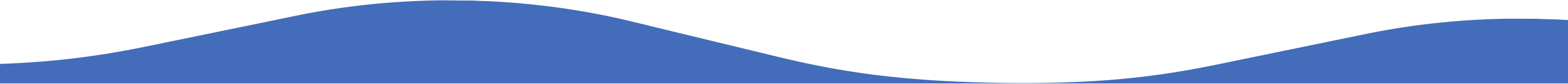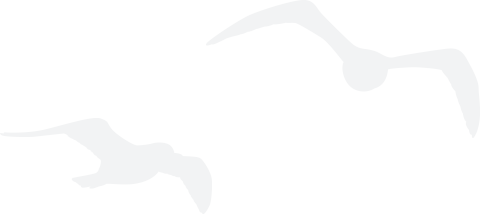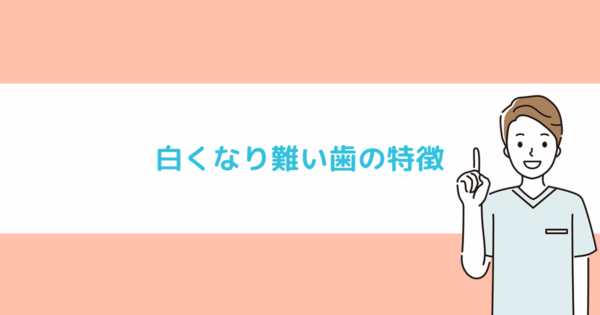
歯の色が気になって白くしたいというときは、ホワイトニングを受けることで叶います。
しかし、中には施術を受けてもなかなか白くならないという人もいるため、要注意です。
どのような歯が、白くなりにくいのでしょうか?
白くなりにくい歯の特徴について解説します。
歯の状態によって効果が出にくい事がある
ホワイトニングは歯を白くするための施術ですが、歯によってはなかなか白くなりにくいことがあります。
白くなりにくい歯とはどのような歯なのか、また、特徴としてどのような点が挙げられるのか解説します。
まず挙げられるのが、著色した色素が濃すぎるケースです。
ホワイトニングは色素が濃すぎる歯にはあまり効果が出ないため、テトラサイクリン歯などは白くなりにくいでしょう。
ちなみに、テトラサイクリン歯とは、抗生物質の影響で着色してしまった歯のことです。
抗生物質の一種であるテトラサイクリンには歯に縞模様の汚れがつくという副作用があり、その状態になった歯をテトラサイクリン歯と呼びます。
縞模様を形成する色はさまざまですが、特に茶色や黒、寒色系の色味になっていると効果が出にくい傾向です。
また、神経を抜かれて黒くなってしまった失活歯も、歯を白くしようとしたときの効果が出にくくなってしまいます。
失活歯は抜髄をして歯に栄養などが届かなくなった歯のことですが、自然と黒ずんでいき、ホワイトニングも効果を発揮しづらいのです。
人工歯には効果がない
虫歯の治療をしたときや歯が失われたときに装着する人工歯も、白くしようとしても効果があまり出ません。
さまざまな素材で作られていますが、素材にかかわらずホワイトニングの効果が出にくいという特徴があります。
ただし、人工歯の場合は、汚れが表面に付着しているだけであるため、クリーニングを受けることで汚れを落とせるでしょう。
また、歯の表面を覆うエナメル質が薄い場合も、ホワイトニングの施術の効果があまり出ないため注意してください。
なお、白くなりにくい歯を白くしたい場合、歯の表面にセラミックを張り付けるラミネートベニヤという治療であれば可能です。
まとめ
ホワイトニングは歯を白くするための施術ですが、ホワイトニングを受けても十分な効果が得られない人もいます。
歯が白くなりにくい例として、歯がテトラサイクリン歯になっているというケースが挙げられます。
また、治療のために抜髄をした失活歯も、ホワイトニングの施術を受けても白くなりにくいでしょう。
エナメル質が薄い歯も、ホワイトニング効果が出にくいため注意が必要です。