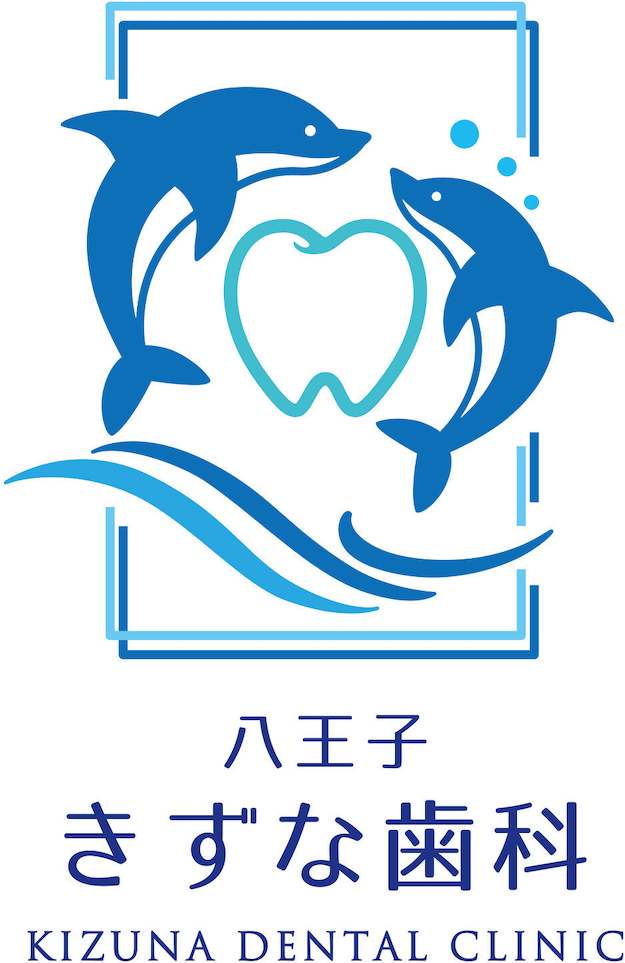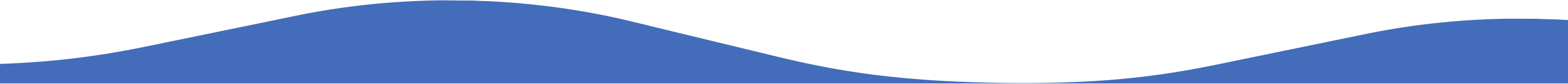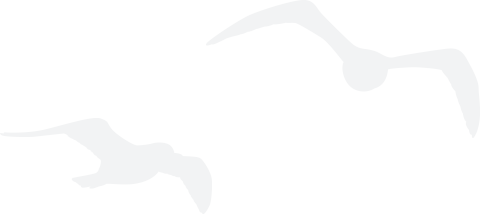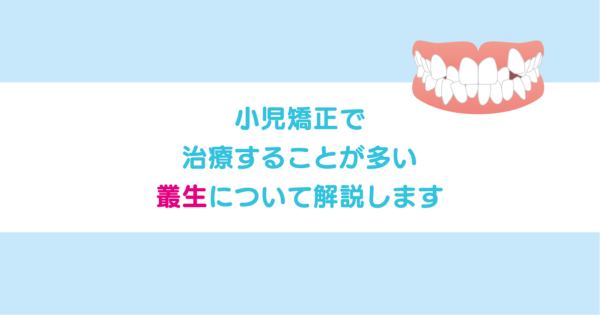
子どもの不正咬合には、よく見られるものがいくつかあります。
特に多く、不正咬合の代表ともいえるのが、叢生です。
しかし、叢生というのがどのような不正咬合か、知らない人も多いでしょう。
叢生がどのような不正咬合で、放置しているとどのようなトラブルがあるのか解説します。
叢生とは?
本来であれば、歯はU字型に並ぶようにして生え、あまり隙間もない状態になるはずです。
しかし、中には歯が前後にずれて生えたり、他の歯と重なって生えたり、斜めに生えたりすることがあります。
歯の生え方がずれたりねじれたりしているなど、通常とは異なる生え方をしているせいで歯列が大きくずれてしまうことを、叢生といいます。
乱杭歯とも呼ばれ、日本ではチャームポイントとして考えられることが多い八重歯も、叢生の一種です。
叢生の主な原因は、歯が顎に対して大きすぎることです。
顎が小さく、歯が綺麗に並ぶスペースが足りないと、歯が他の歯に重なったり斜めになったりと、ずれて生えてきます。
放置した場合に起こるトラブルと対処方法
子どもの歯が叢生になっているとき、放置しているとさまざまなトラブルが起こります。
歯が重なり合っていたりずれていたりすると歯磨きがしにくくなるため、汚れを落としきることができなくなり、虫歯や歯周病、口臭のリスクが高くなってしまうのです。
また、歯並びがずれていると食事の際にしっかりと噛むことができなくなるので、咀嚼が不十分なまま飲みこむこととなります。
食べたものが十分に細かくなっていないため、胃腸での消化の負担が増えてしまうのです。
また、噛む時に顎にかかる負担が大きくなり、顎関節症の原因となることもあります。
不自然に力を入れて噛むことになるので、血流が悪化して頭痛や肩こりを引き起こすかもしれません。
叢生を治す方法として、矯正治療があります。
矯正治療にはいくつかの種類がありますが、基本的なものとして、歯の表側に金属ブラケットとワイヤーを装着するワイヤー矯正や、裏側に同様の装置を装着する裏側矯正が挙げられます。
また、歯が並ぶスペースが足りない場合、成人していれば何本かの歯を抜歯して歯が並ぶスペースを確保しますが、子どもの場合は顎の幅を拡大することも可能なので、抜歯をする必要がありません。
まとめ
叢生は、乱杭歯とも呼ばれる歯並びが乱れた状態です。
叢生の状態で放置していると、他の歯には余分な負担がかかってしまうこととなり、咀嚼も不十分になって胃腸への負担も大きくなります。
叢生を治療するには、ワイヤーを使用した矯正を行うことが多いでしょう。
また、大人の治療では抜歯が必要なケースも多いのですが、子どもの場合は歯並びを拡大することもできるため、抜歯をする必要はありません。