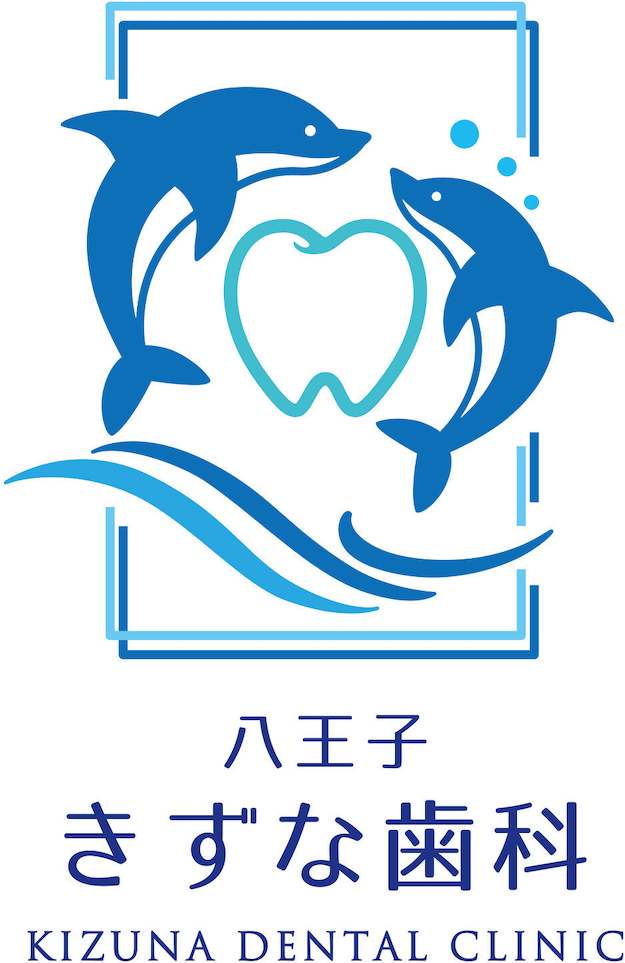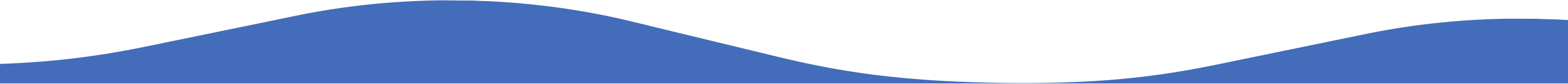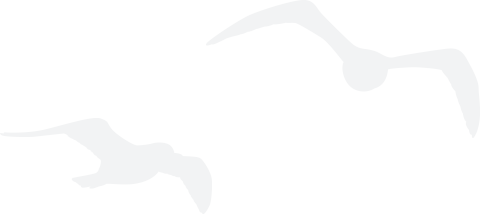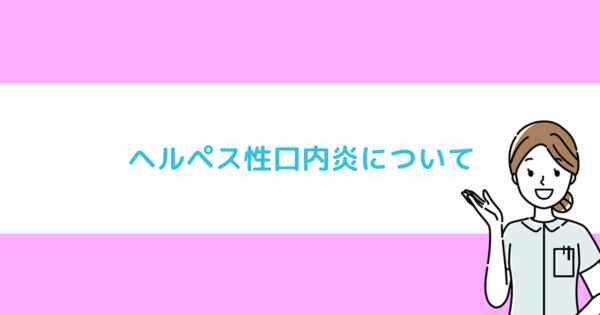
口内の頬や唇などの粘膜にできる炎症を口内炎といい、いくつかの種類があります。
今回取り上げるのは、その一種であるヘルペス性口内炎です。
ヘルペス性口内炎の主な特徴や治療方法について解説します。
ヘルペス性口内炎とは?
ヘルペスウイルスに感染したことで、ウイルスの症状として発症した口内炎はヘルペス性口内炎と呼ばれるものです。
ウイルスに感染した場合、症状は歯茎など口内だけではなく唇の外側や喉の近くにある粘膜など、身体の様々な場所に現れます。
特に、生後半年から3歳までの乳幼児は感染しやすいといわれているため、注意が必要です。
感染した場合には、赤く腫れたり強い痛みが出たりします。
また、あるいは発熱やリンパ腺の腫れ、発心などの症状が出ることもあります。
一度感染すると、完治した後でも免疫力が低下したタイミングで再び発症することが多い口内炎の一種です。
ヘルペス性口内炎の原因となるのは、ヘルペスウイルスに感染している人や、ウイルスが付着しているものに触れてしまうことです。
特に、感染している人やウイルスが付着しているものが粘膜と接触した際に、感染するリスクが最も高くなります。
一度感染すると、ウイルスを保有したままになってしまうため、免疫力が低下した時に繰り返し発症してしまいます。
感染したことがある大人が乳幼児に食事を与える際は、感染しないよう十分に注意しなくてはなりません。
ヘルペス性口内炎の治療方法
ヘルペス性口内炎になった場合、ヘルペスウイルスに感染していることが原因となるため、治療する際は医療機関で適切に処置してもらわなければなりません。
自己判断で受診せず自然に治るのを待っていると、ウイルスが家族をはじめ、身近な人に感染してしまう可能性もあります。
通常の口内炎であれば自然と治りますが、ヘルペス性口内炎の場合はなるべく早く治す必要があります。
病院を受診して完治したと診断されるまでは、食器やタオルを共有しないよう細心の注意を払いましょう。
子どもであれば、治るまで学校などを休ませることも検討してください。
まとめ
ヘルペス性口内炎は、口内炎の中でもヘルペスウイルスが原因となっている病気です。
特に、生後半年から3歳までの子どもによく感染します。
一度感染するとウイルスを保有したままになるため、大人が感染した場合は子どもに感染しないよう、きちんと治療を受けなければなりません。
自己判断で自然に治るのを待っていると他の人に感染してしまうため、専門医の治療を受ける必要があります。