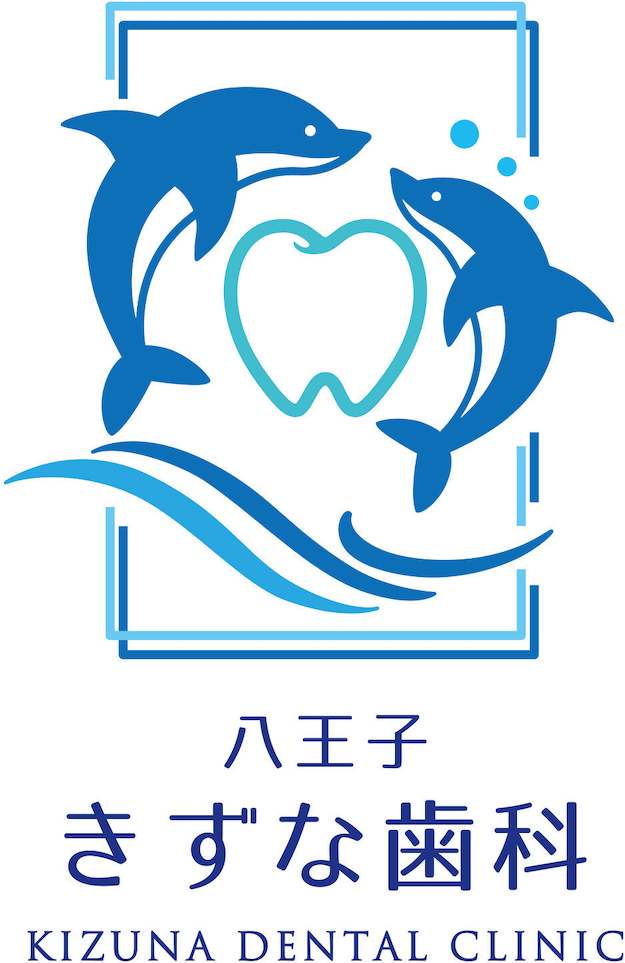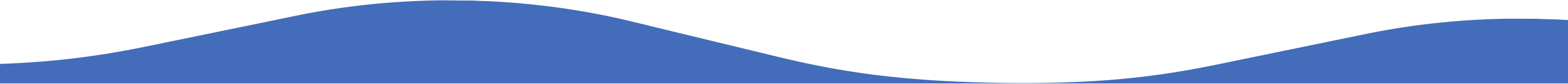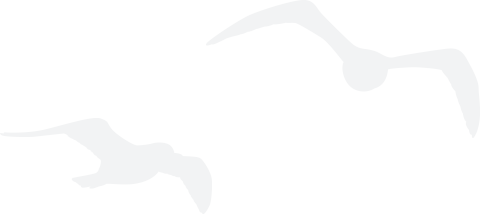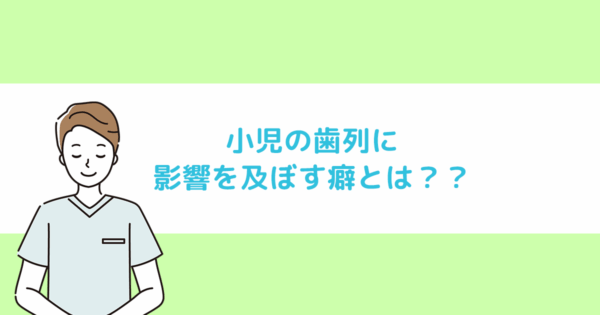
子どもの歯並びが悪くなる原因には、歯や顎の大きさなど先天的なものがあります。
それだけでなく、癖など後天的な原因もあるため、注意が必要です。
特に、歯列に影響を及ぼして歯並びを悪化させる癖は早い段階で改善したほうがよいでしょう。
今回は、小児の歯列に影響を及ぼす癖とは何か、解説します。
子どもの歯列に影響を与える癖は?
小児の歯列に影響を与える癖として、指しゃぶり、舌癖、口呼吸、唇や爪を噛む癖、頬杖、異常な嚥下などさまざまなものが挙げられます。
歯列に悪影響を与える癖のことを口腔悪習癖といい、歯や顎の成長に不規則な力を加えることで、出っ歯や叢生、開咬などの不正咬合を引き起こすのです。
乳幼児期から始まる癖は、顎の骨の成長が著しい時期に特に大きな影響を与えるため、早期の改善が肝要です。
主な口腔悪習癖と与える影響について解説します。
まず挙げられるのが、指しゃぶりです。
指を吸う力で上顎の歯が押し出され、出っ歯や歯列が狭くなる原因になります。
舌の位置が不適切になる舌癖も口腔悪習癖の1つです。
舌が前歯を押したり歯の間に挟まったりすることで、出っ歯や開咬を引き起こす原因になります。
また、舌の機能が低下して舌の位置がだんだんと下がる、低位舌にも注意が必要です。
口呼吸をしていると舌が下がってきて前歯を内側から押し出すため、不正咬合の原因になるでしょう。
唇や爪を噛む癖がある場合は、歯に過度な負担がかかるため、出っ歯や叢生の原因となります。
頬杖も代表的な口腔悪習癖です。
片方の顎に継続的な力が加わることで歯並びが歪んでしまうでしょう。
食べ物を飲み込む際に舌が前歯を押し出す異常嚥下癖は、出っ歯や開咬を引き起こす原因となります。
癖を改善するには?
小児の歯列に影響を与える癖を改善するためのポイントは、早期発見と改善です。
乳幼児期から始まる癖は影響が大きいため、早いうちに習慣を見直すことが大切です。
また、根本原因の探求も欠かせません。
なぜなら、癖は寂しさや不安など、心の問題が背景にあるケースがあります。
そのため、根本的な原因を明らかにして子どもに安心感を与え、ストレスを軽減することが大切です。
自力での改善が難しい場合には、矯正装置を使ったり、MFTなどの専門的なアプローチが必要になったりすることがあります。
悪影響となる癖を改善して正しい口腔機能を習得することで、歯並びを良くすることができるでしょう。
まとめ
小児の癖に悪影響を与える癖には、指しゃぶりや口呼吸、舌の癖、姿勢の悪さや頬杖などさまざまなものがあります。
原因の違いによって歯列の悪さに違いが生じることがあり、たとえば指しゃぶりは出っ歯や歯列の狭さなどの原因になるのです。
根本的な原因を明らかにして癖を改善し、正しい口腔機能を習得することができれば、将来の歯並びに好影響を与えます。