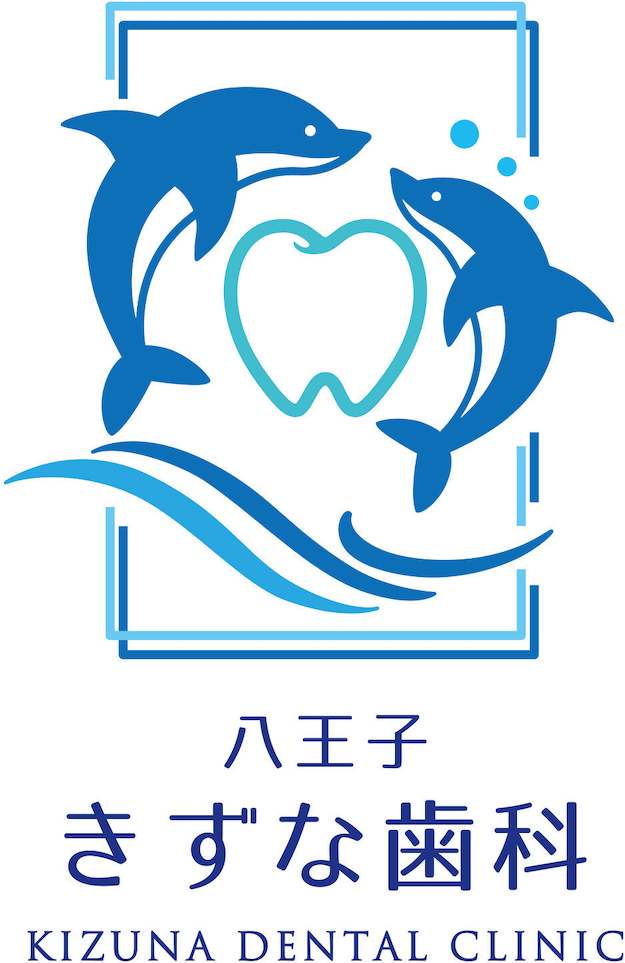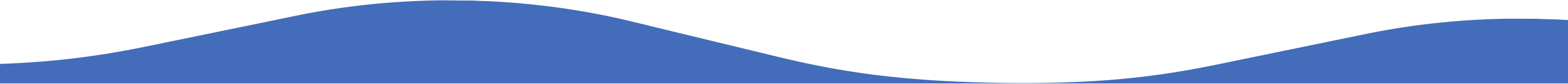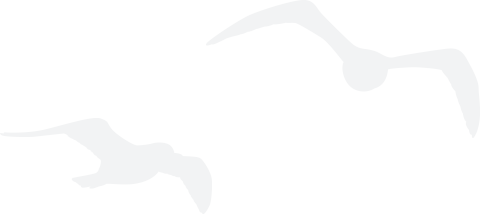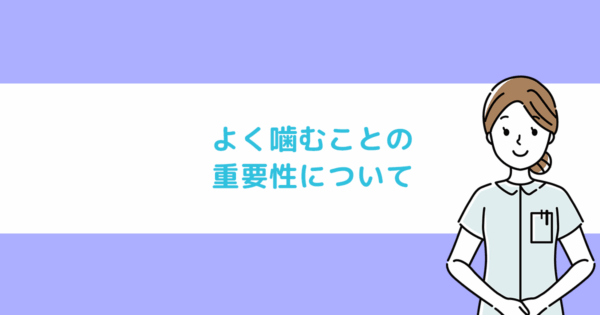
食事の際はよく噛むように言われますが、食べ終わるのに時間がかかるうえに、顎も疲れてしまいます。
そのため、つい早食いになり、あまり噛まずに飲み込んでしまう人は多いでしょう。
実は、よく噛むことには重要な役割があるため、しっかり咀嚼したほうがよいのです。
今回は、よく噛むことの重要性を解説します。
よく噛むことで何がある?
子どもの頃に、「よく噛んで食べましょう」と教えられた人は多いのではないでしょうか?
それほど噛まずに食事をしても、特段の支障が出たことはない、という人もいるかもしれません。
それでもよく噛むよう言われるのは、メリットがあるからです。
まず挙げられるのは、消化に関するメリットです。
よく噛んで食べると食べ物を細かく噛みくだくことができるため、胃腸で消化するのを助けることにつながります。
また、肥満防止につながる点も、メリットといえるでしょう。
よく噛み、ゆっくりと食べると、食べる量が少なくても満腹感を得られます。
そのため、食べ過ぎによる肥満を防止できるのです。
さらに、脳の活性化につながることもメリットの1つに挙げられます。
よく噛むことで脳の血流が増え、脳細胞の動きも活発になることが理由です。
脳の働きが活発になると、集中力や記憶力、判断力などの向上に期待できるでしょう。
加えて、口の健康につながることも、メリットです。
噛むことで唾液の分泌が促進され、食べかすや細菌を洗い流すことができます。
その結果、虫歯や歯周病などの予防はもとより、口臭の悪化も防げるのです。
ほかに、がん予防につながる可能性もメリットといえます。
唾液中の酵素には、食品に含まれる発がん物質の働きを抑制する可能性があるため、健康につながると考えられるのです。
よく噛むことを実践するには?
よく噛むことを習慣づけるには、「噛ミング30(カミングサンマル)」を意識することが重要ですが、聞いたことがない人もいるでしょう。
「噛ミング30」とは厚生労働省が展開する運動で、一口あたり30回以上噛むことを目標に掲げるものです。
食を通じて健康寿命を延ばすことができるため、子供から高齢者まで食育を推進することを重視しています。
既述したとおり、よく噛むことで満腹感を得やすくなるため、メタボリックシンドロームの方や予備軍の方も「噛ミング30」を意識しましょう。
さらに、生涯を通じてよく噛めるよう歯科医院の定期検診に通い、歯を長く健康に保ってください。
まとめ
よく噛むことで、食べ物を細かく砕き、胃腸の負担を軽減できます。
また、脳にも刺激を与え、その働きを活性化させることができるのです。
よく噛むことは、唾液の分泌促進にもつながります。
さらに、満腹感を得やすくなるため、食事量を減らして肥満を予防できるでしょう。
厚生労働省でも「噛ミング30」という運動を展開し、よく噛むことを推奨しています。
歯の健康を守り噛める状態を保ちつつ、一口ごとに30回以上噛むことを意識してください。