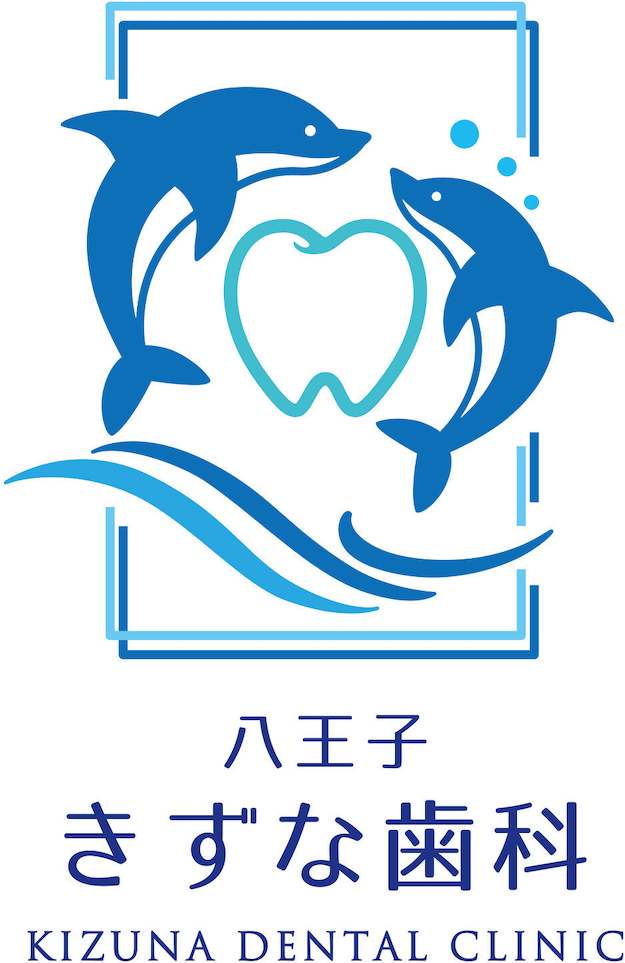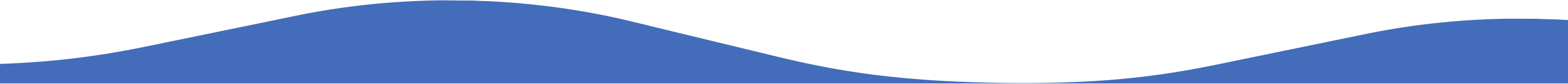妊娠中は、体調が崩れやすく体にもいろいろな変化があります。
口腔内においても、虫歯や歯周病になるリスクが高くなるといわれていますが、原因は何でしょうか?
また、虫歯や歯周病は胎児にも影響を及ぼすことがあります。
虫歯や歯周病のリスクが高くなる原因と、胎児にどう影響するのかを解説します。
虫歯や歯周病のリスクが高まるのはなぜ?
妊娠の経験がある人のほとんどは、悪阻(つわり)も経験しているでしょう。
悪阻がひどくなると食べられるものが限定されるだけでなく、歯磨きもつらくなってしまうことがあります。
妊娠中に虫歯のリスクが高くなる原因は、悪阻です。
悪阻がひどくなると、嘔吐することが増えてしまいます。
そして、胃の中にある食べたものと胃液が一緒に吐き出されます。
胃液は食べ物を溶かす酸性の液体です。
吐いたとき歯に付着すると、表面のエナメル質が溶かされてしまいます。
それだけでなく、口内を酸性にして虫歯菌が活動しやすい環境を作ってしまうのです。
本来であれば、唾液が酸を中和して口内環境を中性に近づけますが、妊娠中は唾液の分泌量が減少するため、唾液による中和がしきれません。
したがって、妊娠中は虫歯になりやすいのです。
また、妊娠中は歯周病にかかりやすくなります。
ただし、歯周病の原因は虫歯とは異なり、悪阻ではありません。
なぜなら、歯周病菌は酸性の環境ではなくアルカリ性の環境下で活動するためです。
よって、悪阻によって口内環境が酸性に傾くと、歯周病になるリスクは下がります。
しかし、妊娠性歯肉炎になる可能性が高まるため、注意が必要です。
胎児への影響は?
妊娠中に歯周病になると、胎児にも影響を及ぼします。
歯周病菌が女性ホルモンによって増殖することで、早産や低体重児出産を引き起こすことがあるのです。
子どもを健康な状態で産みたいのであれば、妊娠前から虫歯や歯周病の予防をすることが大切です。
もしも妊娠中に虫歯や歯周病になった場合には、できるだけ早く治療しましょう。
ただし、安定期に入る前は体調が不安定になりやすく、治療を受けるのがつらいこともあるため、無理は禁物です。
出産後は子どもに虫歯菌を感染させないように注意してください。
実は、生まれたばかりの赤ちゃんの口内には虫歯菌が存在していません。
しかし、離乳食が食べられるようになった頃に、保護者の箸やスプーンで食べ物をもらった時などに、唾液から虫歯菌が感染してしまう恐れがあります。
両親や祖父母などから感染した虫歯菌により、子どもが虫歯になってしまうのです。
子どもを虫歯にしないためにも、保護者はあらかじめ虫歯を治療しておくことが大切です。
出産後も歯科医院で定期検診を受けて、虫歯が見つかった場合には早期治療をしてください。
まとめ
妊娠中に虫歯のリスクが高まると言われるのは、つわりで嘔吐したときに胃液が歯に付着し、歯を溶かしてしまうとともに口内を酸性に変えて、虫歯菌が活動しやすい環境になってしまうからです。
歯周病菌は酸性の環境では生きていけないものの、妊娠中は歯肉炎に似た妊娠性歯肉炎にかかることが多く、将来的に悪化して歯周病になることがあります。
妊娠中に虫歯や歯周病になると胎児にも影響するため、きちんと予防しましょう。